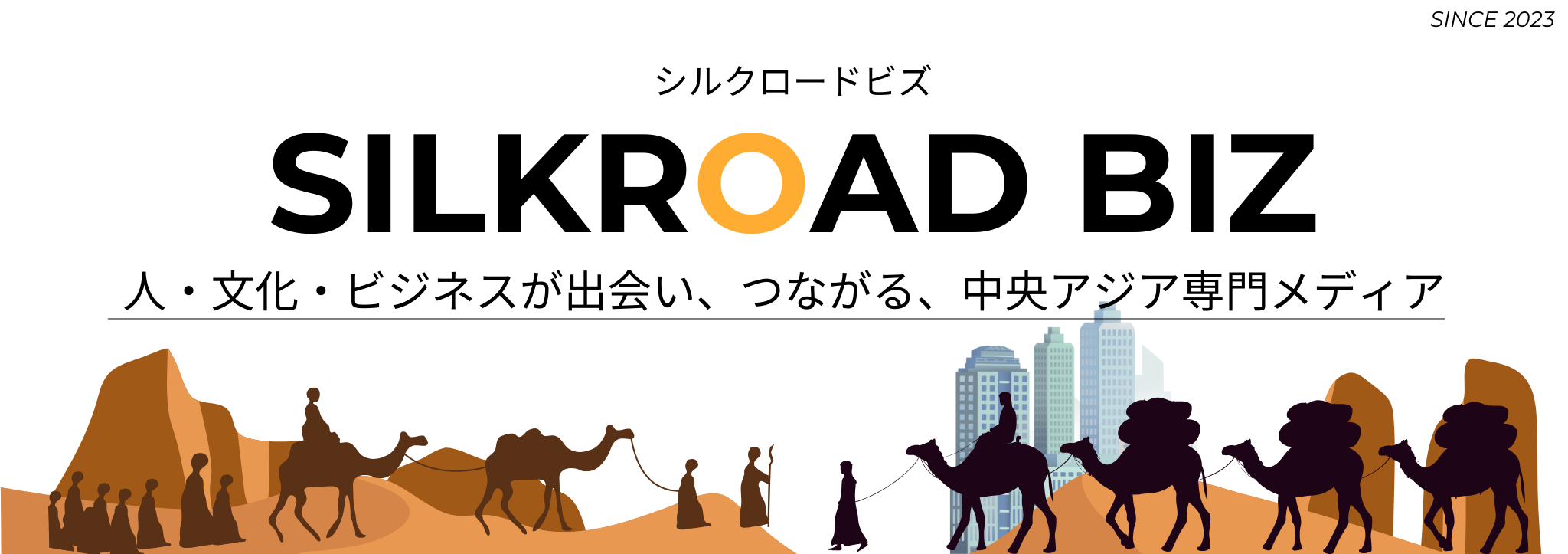今回はいつものBIZとは少し角度を変えて、
アカデミックな観点から中央アジアの魅力についてお届けします。
「中央アジアの考古学」をテーマに
龍谷大学 龍谷ミュージアム教授の岩井俊平先生にお話しを伺いました。

岩井 俊平
龍谷大学 龍谷ミュージアム教授(学芸員)
<略歴>
京都大学大学院文学研究科 博士後期課程単位取得満期退学。
東京文化財研究所などを経て現職。
専門は中央アジア考古学。
中央アジア史(イスラーム化前:1世紀~8世紀頃)に、考古学的手法からアプローチする研究を展開。アク・べシム遺跡(キルギス)、ダルヴェルジン・テパ遺跡(ウズベキスタン)、アジナ・テパ仏教寺院址(タジキスタン)、バーミヤーン遺跡(アフガニスタン)等で発掘及び保存事業に参加。
=
少し難しそうなテーマですが、岩井先生が他の地域と違って魅力や中央アジアの歴史に興味をもったきっかけについてお話をしてくださいました。
是非ご一読ください!
編集部:岩井先生、今日はよろしくお願いいたします。
はじめに先生が中央アジアに興味を持たれたきっかけを教えてください。
岩井先生:一番昔の記憶でいうと、わたしが子供のころにシルクロードブームみたいなものがあって。当時NHKなどで放送されていました。
また、高校時代に世界史を勉強するなかで中央アジアがものすごく曖昧に書かれていたんです。用語とか。その時に「この地域って歴史がまだ はっきりわかってないんだなぁ」と思い惹かれた記憶があります。
編集部:先生は京都大学の文学部に進まれるわけですけども、既にその時にはご自身が中央アジアの研究をすることを意識されていたのですか。
岩井先生:漠然とシルクロードの歴史への憧れみたいなものはあったので、その地域を研究するなら京都大学が良いというのは聞いていて、がんばって勉強しました。
3回生に上がるときに専門を選択するため、そのときにはっきりと決めた感じです。
編集部:受験時にそこまで将来を見据えて大学を選ぶ学生はあまり多くないと思います。さきほども中央アジアに興味をもつきっかけを伺いましたが、それ以外にも何か歴史に興味をもつきっかけはありましたか。
岩井先生:もともと小学生、中学生のころから歴史に興味を持っていました。次第に大陸の方、中国に興味・関心がむいたのですが、思い起こせば漫画「三国志」(横山光輝)からは大きな影響を受けたと思います。「三国志」をきっかけに歴史に興味を持ったのかもしれません。

編集部:わたしも兄の影響で三国志読みました。大好きな歴史漫画です。
そのような経緯から歴史に興味を持たれたわけですね。
そんな岩井先生にとって、中央アジアが他地域より魅力的なのはどのような点ですか。
岩井先生:さきほど高校時代のことでも触れましたが、やはり「わからないことが多い」という点は大きな魅力の一つです。特にいま研究をしている紀元前後の中央アジアについては文献資料がほとんどありません。
編集部:一方、中国史に関する資料・文献は多くあります。地域において資料・文献にかたよりがあるのは、争いの歴史のなかで破棄や破壊された結果なのでしょうか。
岩井先生:一概にそうとも言えません。実は中国やローマが特殊なんです。実際、中国やローマ以外の地域では1世紀や2世紀のころに現地の歴史を書き残すといったことは珍しいことなんです。特に中央アジアは遊牧民族が多く、記録に残すということが少なかったのかもしれません。
中国やローマの文献には中央アジアについて語られている部分もあるのですが、偏見に満ちた記載や間違った情報も多くみられ、その当時のことを正確に理解する資料が少ない印象です。
編集部:岩井先生は実際に中央アジアに行かれて発掘されています。そのときの印象深いエピソードなどあれば教えてください。
岩井先生:そうですね、、、キルギスにアク・べシム遺跡という遺跡があるのですが、そこから屋根に使われる瓦が出てきたときは興奮しました。帝京大学のチームが発掘していて、出土の瞬間に立ち合ったわけではなかったのですが、瓦はすべて唐時代の技法で作られたものでした。この時代は唐の出先機関(軍事拠点)がここにあった、とはいわれていたのですが、これだけの量の瓦が出土するということは、わざわざ唐から職人をつれてきて、瓦葺きの建物を作らせていたわけです。
発掘作業は基本的に金銀財宝のようなお宝が出てくるわけではありません。ただ例えば日干し煉瓦を積んだ建物が出てきた、となるとそこから当時の生活や背景が推測できワクワクするわけです。

編集部:帝京大学の話もでましたが、中央アジア研究において横のつながりも強いのでしょうか。
岩井先生:はい。大学間の枠組みでもありますが、中央アジアは研究者が多いわけでもないので、個人的なつながりが強いです。実際に帝京大学の山内和也先生は、昔から中央アジア、アフガニスタン、イランのあたりの考古学やっておられ、先生とは同じ職場で上司と部下という関係で一緒にアフガニスタンの研究をした時期もあります。
編集部:中央アジアへよく行かれる先生ですが、中央アジアの好きな料理を教えてください。
岩井先生:まず発掘に行く際はどのような状況か説明します。
現場によってさまざまですが、遺跡の近くにホテルなど多くの部屋がある建物を貸し切ります。そこにスタッフを雇って、料理もつくってもらうことになります。よって自然とロシア料理や中央アジア料理が提供されます。スタッフが作ってくれる、プロフやラグマンは好きです。
わたしがはじめて中央アジアに調査に行ったのは1999年です。その頃に提供されていたラグマンは表面に1cmくらい油がはっているような状態で(笑)、結構しんどかった思い出があります。その頃と比べると今はとてもおいしい料理を提供してもらっています。
編集部:いざ調査へ行くとなるとどれくらい滞在されるのですか。
岩井先生:大体1か月くらい滞在します。調査中は朝起きて発掘作業をはじめ、それを一日中やって、その繰り返しなわけです。だから食事はものすごく楽しみになるんです。たまにシャシリク(羊や牛などの串焼き)買ってきてみたいなときは、めちゃくちゃ盛り上がります(笑)

編集部:シャシリクうまいですよね、、僕も大好きです。
ありがとうございます。
それでは、今後の研究や取り組みについてお聞かせください。
岩井先生:私の場合は考古学なので、継続して発掘現場に行きたいです。
ただ発掘作業するとなると、やっぱりお金が必要なわけです。日本学術振興会などに研究費として申請するわけですが、毎年予算取りができるかは保証がない状況で、そこは不安定なところではあります。

編集部:なるほど。SILKROAD BIZでは「つながる」をテーマにしています。
中央アジアを研究されている岩井先生に協力いただける企業や団体があれば、と思います。
岩井先生:はい、そうですね。わたしの場合はどうしても歴史がテーマになるわけです。
例えばウズベキスタンのサマルカンド周辺は、ソグド人と呼ばれる人々が暮らしていた場所です。彼らが使っていたソグド文字が焼き印された香木を、奈良の法隆寺がかつて所蔵していた事実もあり、日本と歴史的なつながりもある地域になります。このようなことに興味を持っていただき、企業の方もそうですし、実際に一般の方々にも遺跡に足を運んでいただけたらうれしいです。
編集部:わかりました。
まだまだ解明されていない部分が多い中央アジアの歴史の魅力について、岩井先生にお話し伺いました。今日は先生の研究内容というよりは、中央アジアに興味を持つきっかけについてお話を伺うこととなりました。今後も引き続き、SILKROAD BIZとして先生の活動を追わせてください。
本日は貴重なお時間、ありがとうございました。
===
<余談>
編集部:タジキスタン産ピスタチオの残渣でつくったクッキーがあるんです。

岩井先生:これはタジキスタンのアジナ・テパの涅槃像ですね(笑)

編集部:以前インタビューをさせていただいたJICA原口さんがタジキスタン産ピスタチオ残渣をつかった「仏像クッキー」をつくっています。もし龍谷ミュージアムさんの何かのイベントで使えることあれば、ご使用ください!
岩井先生:お約束はできませんが(笑)
ミュージアムサイドも興味を持てばいいのではないでしょうか。またお話してみてください。